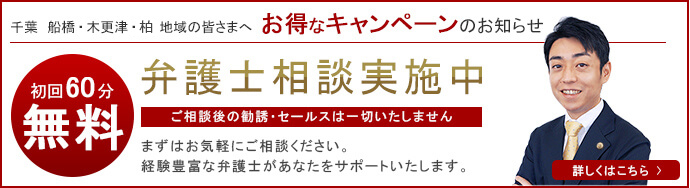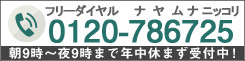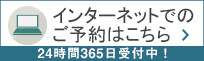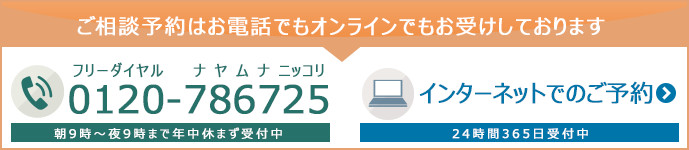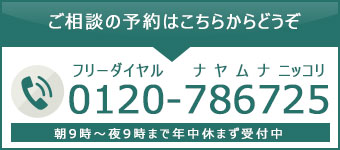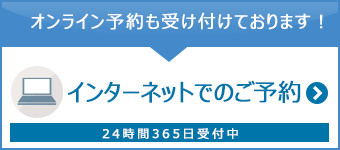懲戒解雇の手続きとは
懲戒解雇にあたっては以下のような手続を経て行う必要があります。
1.就業規則の規程
懲戒解雇の事由は就業規則に明記され、それが従業員に周知されていることが必要です。
例えば、客観的に誰が見ても企業の秩序を乱すような行為(横領など)を行ったとしても、「刑事犯罪にあたる行為を行なった者は懲戒解雇」といった内容が記載されていなければ、懲戒解雇には出来ません。
従業員が10名以下であり、就業規則の作成義務が無い企業などは、そもそも就業規則が無いこともあります。
このような場合、従業員の懲戒をめぐってトラブルが起こる可能性が大きいので、注意が必要です。
就業規則にも雇用契約にも懲戒解雇事由が明記されていない場合、どんなに悪質な行為をしたとしても、懲戒処分として解雇することはできません。この場合は普通解雇の手続により処理することになります。
2.適正な手続
懲戒解雇は労働者に対するペナルティであるため、原則として処分を行う前に対象者に弁解の機会を与える必要があります。
就業規則や労働協約に懲戒解雇を行う際の手続について特に定めがある場合には、その定めに沿って手続を進めなければなりません。
このような手続を履践しない場合には、適正な手続を踏んでいないものとして、懲戒解雇は無効となる可能性があります。
また、懲戒解雇の原因となる事由があってから、何らの処置もせず長期間が経過した場合、その後に処分を行うことは原則として認められません。
懲戒の対象となる行為があった場合、速やかに対処することが必要です。
3.解雇の合理的理由・社会的相当性
懲戒解雇の合理的理由とは、対象者の行為が企業秩序を著しく乱す行為であったかどうか(具体的には、規定された懲戒解雇事由に該当するかどうか)の問題です。
仮に合理的理由があり、懲戒解雇事由に該当する場合でも、懲戒解雇という選択が社会的に見て相当かどうかも問題となります。
例えば、企業秩序を乱したといえるが、会社に実損が生じていないとか、解雇せずとも秩序の回復が可能であるという場合は、懲戒解雇の社会的相当性は否定されます。
また、後に裁判に発展した場合に備えて、懲戒解雇の根拠となる事実を客観的に証明することのできる証拠を集めておく必要があります。
事案にもよりますが、出勤簿・タイムカード・勤務記録、関係者の陳述書、警察の証明書(刑事事件の場合)、懲戒行為に関連する社内資料などについて、可能な限り多く集めて保管しておいた方が良いでしょう。
また、懲戒解雇の場合、解雇当時に会社で把握していなかった事実を事後的に裁判で追加主張することは認められていません。当該従業員が他にも懲戒事由に該当する行為を行っていないか、十分に調査しておく必要があります。
4.懲戒解雇の具体例
以下のような場合、懲戒解雇の相当性が認められると考えられます。
(1) 業務上の地位を利用した犯罪行為をした場合
経理職員が不正経理によって横領行為をしていたり、営業職員が架空取引を計上して利益を得ていたという場合は、懲戒解雇となるのが一般的です。
このような行為は会社に対する深刻な背信行為であり、かつ会社の損害も通常大きなものとなりますので、懲戒解雇の理由には十分に当てはまると考えられます。
ただし、犯罪行為を理由に懲戒解雇とするためには、十分な客観的証拠を収集して、等が従業員に弁明の機会を設ける必要があります。先に刑事告訴をした上で社内での処分を検討する、といった慎重な対応をとった方が良いでしょう。
(2) 会社の名誉を著しく害する重大な犯罪行為
業務とは関わりのない私生活上の行為であっても、殺人、強盗、強姦などの重大犯罪や会社の名声を著しく貶めるような犯罪行為がある場合(例えば、鉄道会社の駅員が常習的な痴漢行為を行い逮捕された等)、懲戒解雇が認められます。
(3) 経歴の重大な詐称
会社の採用判断に重要な影響を与える経歴(採用要件となっている学歴・特定資格の保有の有無等)を詐称していた場合、会社の採用プロセスへの深刻な背信行為として、懲戒解雇が許される場合があります。
(4) 長期間の無断欠勤
長期間の無断欠勤は会社にも損害を与えます。
例えば、対象者が正当な理由なく1ヶ月以上無断欠勤を続け、度重なる出勤命令も拒否し続けた場合には、懲戒解雇が認められる余地があります。
(5) 重大なセクハラ・パワハラ
セクハラやパワハラは、通常は一回で懲戒解雇とすることはできません。
ただし、強制わいせつや強姦に類似するようなセクハラ行為や恐喝や傷害に至るようなパワハラの場合は、事案の悪質性から懲戒解雇が認められる可能性があります。
実際にこのような行為が行われ、被害者が被害届を足した場合、刑事事件として扱われ、加害者が逮捕される場合もあります。
(6) 懲戒処分を受けても同様の行為を繰り返す
軽度のパワハラ・セクハラ、単純な無断欠勤、業務命令違反等については、当初は注意指導や軽微な懲戒処分 (訓告や減給など)がされることになります。
このような是正措置を講じても本人がこれを改善せず、同様の行為を繰り返す場合は、事案が悪質であるとして懲戒解雇が認められる可能性があります。
5.解雇予告と解雇予告手当
懲戒解雇も解雇の一種であるため、対象となる従業員に30日前に解雇予告を行うか、30日分以上の平均賃金の支払いをすることが必要となります。
懲戒解雇の場合、所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請を行うことで、解雇予告手当なしで直ちに解雇することもできます。
もっとも、申請手続にかかる手間や時間の関係から、実務上は解雇予告手当を支払って解雇することが多いといえます。
このように、懲戒解雇は解雇の中でも特に厳格な要件を満たす必要があり、慎重な手続きを経て行う必要があります。
リスク回避の点から、懲戒解雇以外の解雇方法を選択した方が、会社にとっての損失を最小限に抑えられる場合もあるでしょう。
【注意】
弊所では、残業代請求を含む労働トラブルについて、会社経営者様からのご相談(会社側のご相談)のみをお受けしております。 利益相反の観点から、従業員・労働者側からのご相談はお受けしておりませんので、予めご了承ください。
以下、詳細ページのご案内です。
お得なキャンペーン・ご相談予約はこちら